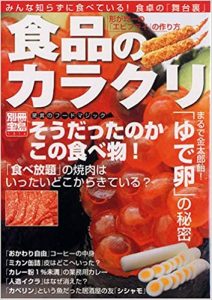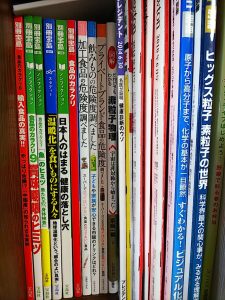前回の続き・・・。
市販のカレールウの中にカレー粉あるいはカレーパウダーはどのくらいの分量で入っているのだろうか?
チト、調べてみた・・・□_((ヾ(・ω・*)カタカタ
こんな文字が躍っているサイトがよく見かけられた・・・。
『カレールーの主原料は固形脂肪で、カレー粉はどこのカレールーでも、 5% ~ 10% 程度です。カレー粉が 5% ~ 10% でも入っていればまだ良い方ですが、中には1% も入っていないカレー粉があります。学校給食にも納入されているあるメーカーのカレールーがそれです。』
どうやらこのネタの出処は、宝島社から出されている「別冊宝島 食品のカラクリ~驚異のフードマジックそうだったのかこの食べ物!~」から来ているようだ。
真偽を質すために、早速、A〇A〇O〇で購入するために検索・・・[PC]ヾ(-Д-*)ウーン…
2006 年 7 月 15 日発行の物なので、流石に新刊は無かった・・・(o´・ω・)´-ω-)ウン
中古で売っていたので注文・・・(〇`ω´)ノ凸凹。о○{ポチットナ}
翌日には、当該本が届けられる。
早速、確認すると、“外食のヒミツ❸”で、『カレー粉含有率 1% でも立派な「カレーライス」とは』とはというタイトルで書かれていた。
別冊宝島、結構愛読しています(笑)。
宣伝兼ねて、ちょっとだけ拝借します・・・m(_ _)m
サブタイトル:カレールーのブレンド勝負。「国民食」はこう作られる。
『今やすっかり日本人の食生活に溶け込んだカレーライスだが、・・・(中略)・・・。
レストランでも家庭でも、カレールーから作るのが大半。
カレーチェーン店でも、市販のカレールーが使われているのは公然の秘密である。
食品会社が作るカレールーをいかに混ぜ合わせて使うかが、唯一コックの腕の見せ処であるといっても過言ではない。
例えば、レストランのビーフカレー、ポークカレーでも、中の肉はカレーが出来てから入れているから、肉汁の本当の旨さを味合うことは無理だ。
カレールーの主原料は固形脂肪で、カレー粉はどこのカレールーでも、 5% ~ 10% 程度である。
(中略)
カレー粉が 5% ~ 10% でも入っていればまだいいが、中には 1% も入っていないカレー粉があるから驚く。
学校給食にも納入されているあるメーカーのカレールーがそれ。
原材料は、小麦粉 51.5% 、油脂 27.2% 、調味料(化学調味料等含む) 19.2% 、脱脂粉乳 1.9% 、香辛料少々、カレー粉少々となっている。
少々と言うのは、1% 未満のことだが、カレー粉が 1% も入っていなくて、カレーというのはいかがなものだろうか?』
末娘に聞けば、子供等にとって、学校給食でカレーは断トツの人気メニューらしい・・・。
まあ、かなり古いデータにはなるのだが、宝島社が書かれていることが事実であれば、カレーを食べるのにカレールーを使うのは意味が無くなってくるようだ・・・ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…
古くから言われているが、カレーは複数のスパイスから作られ、そのスパイスは、漢方薬として使われているものも多く、健康への効果が期待できる料理なのだ。
現に、“カレー + 健康”というキーワードで検索してみると・・・。
Yahoo!で、約 62,900,000 件もHitするのだ・・・!
更に、美容効果もあるらしく、“カレー + 美容”というキーワードで検索してみると・・・。
Yahoo!で、約 42,500,000 件もHitするのだ・・・!
その効果は・・・。
カレーに詳しい漢方専門医の丁宗鐡(ていむねてつ)先生によると・・・。
1. 食欲の調整(抑制と亢進)
2. 消化促進作用
3. 新陳代謝促進効果
4. 抗菌活性作用
5. 自律神経調整作用
6. 中枢神経刺激作用
7. ホルモン分泌刺激作用
8. 循環促進作用
9. 塩分を控えられる
10. 寒暑に対する適応力が上がる
・・・とカレーに期待できる 10 大メリットを挙げている。
前回、取り上げた 4 種のスパイスだけでも解説しよう。
参考:https://www.bioweather.net/recipe/0707n/0707n_index_e.htm
【レッドチリ】
脂肪を燃やして発汗作用を促すカプサイシンを含むためダイエットに効果があるといわれるスパイス。カレーの辛さを決める重要なスパイスで、量が多いほど辛くなる。唾液や胃液の分泌を促進して消化を高め、食欲増進、抗酸化作用、老化防止などの効能も期待できる。末梢神経を拡張して血行をよくするため、アルコールエキスは神経痛などの温湿布にも利用され、靴下の中に入れてしもやけや凍傷の予防にも使われる。刺激が強いので大量に摂取すると胃や腸の粘膜が炎症を起こすことがあるので要注意。数千種ともいわれる品種があり、同品種では温暖な気候で育つほど辛みが強い。
【ターメリック】
カレー粉の主原料で黄色の色付けに使われ、カレーには欠かせないショウガ科の多年草。豊富に含まれるクルクミンが胆汁の分泌を促して肝機能障害を予防するので、肝機能が強化される。鎮痛、抗酸化作用、殺菌効果があり、皮膚炎の殺菌作用も認められている。漢方では止血効果があるとされている。油によく溶ける性質があり、サフランの代用としても利用され、日本では沢庵漬けにも使われている。スリランカでは布の染色にも利用されている。
【クミン】
古代ギリシャ・ローマ時代から栽培されていたセリ科の一年草で、原産は地中海沿岸地方。カレーの主要なスパイスで、種子はキャラウェイに似た香りと辛みを持つ。辛み成分はクミナール。消化促進や解毒作用があり、下痢や腹痛の治療薬、胃腸内にガス溜まるのを予防する、肝機能を高めるなどの効能がある。
【コリアンダー】
葉や茎に特有の臭気を持ち、秋に同じような臭気を持つ白こしょうに似た実をつけるセリ科の一年・二年草。この臭気は熟すにつれてレモンの皮とセージを合わせたような香りをかもし出す。消化を助けるため胃薬として利用され、食欲増進作用もある。鎮痛、血液浄化、発汗作用があり、かゆみ止めにも応用される。生葉はスープの浮き実に利用される。
何やら、凄いぞ、カレー!!!
次回へ・・・。